こんにちは。
家族問題解決専門カウンセラーの鈴木悦子です。
「毒親育ち」という言葉が世間に認識され始めてから、
「私も、もしかしたら毒親育ちだったのかも・・・」
と心配し、自分を顧みる人が昔に比べて増えたような気がします。
そして、
「私は自分の子どもに対して、毒親には絶対にならない!」
と決意、自分自身を鼓舞し、子育てに専念するお母さんもいらっしゃると思います。
毒親からの影響により毒親育ちの人が毒親になってしまう・・・いわゆる“毒親の連鎖”というもの。
心理学的には親は子どもの絶対的な模範となるので、いつしか親の言動や行動が自分のものとなっている、ということは確かにあります。
しかしそれは絶対的なものでなく、ポイントを意識していくことでその連鎖は食い止めることができるんですね。
今回は、なぜ毒親の連鎖が起こるのか?その背景、そして毒親にならないために大切な考えかたや行動などについてお話していきます。
さらに、たとえ毒親育ちでも親子関係を健やかに保つため、普段からできる工夫もまとめてみました。
毒親からの影響、そしてそれに伴う連鎖について。気になる方はぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
目次
なぜ“毒親の連鎖”は起こってしまうのか?
毒親育ちの人は親から様々な影響を受けていますが、そのなかでも特に恐れているのは、
“自分も子どもに対して同じことをしてしまうのではないか・・・”
という不安や心配ではないでしょうか。
実際、自分では十分気を付けているつもりでも、気がついたら「母親と同じように怒鳴ってしまった」「父親の口癖をつい言ってしまった」など、連鎖のようなことが起こることは少なくありません。
人間の心、深層意識というのは複雑なもので、とくに仕組み的に、
“親からの幼少期のしつけや言葉が無意識の中に刷り込まれる”
というものがあります。
人間の脳という臓器はくり返し聞いた言葉や見た行動に対し、知らず知らず自分のものとしてインストールしていく、という特徴をはらんでいるんですね。
言いかたを変えると、目の前で起きていることは当たり前のものとして記憶しますので、自分が大人になり子育てをする際、気づかないうちに親と同じ行動を再現してしまう、ということが起こってしまいます。
そのようなことから幼少期のインストール経験をもとに、反応としての“連鎖”が起こってしまうと言えるでしょう。
ですが、反応としての連鎖とは言っても解決策が無いわけではありません。
大切なことは、自分がいま毒親から受けた影響をまねている、無自覚で反応していることに気づくこと。それが連鎖を止める第一歩となるでしょう。
毒親にならないために必要な考えかたとは
毒親の連鎖を断ち切るため、そして自分が毒親にならないため、まずやるべきことは、
「自分のなかでの考えかた」
を意識的に切り替えていくことです。
ここからは、どのような自分のなかの考えかたを切り替えていくべきか?お話していきましょう。
1、自分が起こした反応を否定しない
これはいけないと思いつつも、自分が子どもの頃に親から受けたように子どもに対しイライラをぶつけてしまったり、子どもの感情を否定してしまったり、手を上げてしまう、など。
十分気をつけているつもりが気がついたらそのような行動に出てしまい、苦しんでしまうこともあるでしょう。
そして、そんな反応をしてしまった自分自身を責めてしまったり自己嫌悪に陥ったりと、罪悪感で胸がいっぱいになっているかもしれませんね。
ですが、ここで大切なことは、
“自分が起こした反応を否定しない”
ということ。
自分を責めれば責めただけ心は傷ついてしまい、いつしか笑顔は失せ、罪悪感とツラいだけの毎日となってしまうかもしれません。
子どもに対して起こした反応はあくまで“毒親からの影響である”と割り切り、あくまで自分を否定しないことが重要です。
子どもに対して嫌な反応をしてしまいそうなときは、一旦深い呼吸をくり返しおこないましょう。
深い呼吸をくり返すことで頭のなかはリセットされ、気持ちを落ち着かせることができますので。
2、完全で完璧な親は目指さない
毒親からの連鎖を考えれば考えるほど、
「子どもには優しく、ちゃんとした親でいなければ・・・!」
と、強く思ってしまいがちです。
その考えが深くなればなるほど完璧であれ、完全であれ、というように、完全体の親を目指してしまいがちです。
しかし、世の中には完全、完璧というものはなく、人間らしさも損なわれてしまうかもしれません。
大切なことは完全、完璧を目指すのではなく、子どもにとって「安心できる親」なんですよね。
子どもは親の不完全なところやうっかりミスからもいろいろと学び、そんな姿から安心を感じるものです。
子どもが安心していられる雰囲気や笑顔、仕草でいるほうが何倍も大切なことですよ。
3、子どもの感情を否定しない
子どもというのは小さければ小さいほど、感情そのままに生きています。
さっきまで笑っていたのにもう泣いた、先ほどまで泣いていたのにいまは楽しそうに遊んでいる、なんて、一瞬一瞬コロコロと感情が変わりますよね。
子どもが癇癪を起したり、強く泣いているとつい大人の目線で「泣いてはダメ」「怒らないでしっかりしなさい!」と感情を否定してしまいがちです。
子どもにとって親というもの、とくに母親という存在は絶対的なものですので、言われたことに従いながらどこかで感情を封じこめ、いつしか子どもらしさを失ってしまいかねません。
感情を否定するのではなく、なぜその感情でいるのか?考えながら、
「いま悲しいんだよね」
「とっても腹が立つんだね!」
「これはちょっと怖いよね・・・」
など、子どもの感情に寄り添ってあげましょう。
そうすることで子どもは自己肯定感が増し、自然と感情について学びながら活き活きとして子どもに育っていくことは多いものです。
▶ 心理カウンセラー鈴木悦子へのカウンセリング依頼はこちらから
日常で気をつけたい親子関係のポイントについて
毒親の連鎖を止めるには、子どもとの日々の小さな関わりかたが鍵になると言っても過言ではありません。
また、それと同じく自分自身の内面との向き合いかたも非常に重要な要素となります。
ここからは、親子関係はもちろん自分自身との向き合いかたについてもお話していきますね。
子どもの行動を温かく見守る
子どもの行動、とくに小さなお子さんの場合はやることなすことハラハラしてしまうことが多く、つい口は手を出してしまいがちですよね。
もちろん危険な行動や突発的な動きには注意し手を出す場合もありますが、基本は子どもを信頼し、うかつに口や手を出さない、ということが重要になります。
なんでもかんでも親から口や手を出されると子どもの自己肯定感や自尊心、自信などは育ちにくくなってしまい、結果的には親の顔色を伺いながら行動する可能性があります。
これでは毒親の連鎖と言える状態となってしまい、理想とする親子関係からほど遠くなってしまうんですね。
子どもの行動には心配や不安が付きまとうものですが、子どもの心を育むと割り切り、あえて口出ししない、手出ししない、という勇気を持つことを心がけましょう。
「叱る」と「怒る」の違いを理解する
子どもに対して「叱る」と「怒る」、この2つは一見とても似ている感じがしますが、実はまったくの別物です。
「叱る」という行為は相手のためを思い、真剣な眼差しと気持ちで正しいことをしっかりと伝えること。
時間が経ったとき、叱られた本人が叱られた意図を理解し、腑に落としていける状態を指しています。
一方「怒る」というのは相手のためというよりも、自分自身のためのものであり、憤りや憤慨した心を発散して鎮めるためのものです。
怒られた本人はいまいち怒られた意図を理解できず、腑に落とせることなく、自己肯定感や自尊心など削り取られていってしまうものなんですね。
多くの毒親は「叱る」のではなく「怒る」ことで自分の気持ちを発散し、子どもを追い込むことが教育やしつけだと誤認識しています。
これでは正常な親子関係は築かれず、成長期の子どもにとってはデメリットばかりとなるでしょう。
もし、子どもに対して何かを伝えたとき、気持ちがスッキリしたり発散できた感覚があれば、それは「叱って」いるのではなく「怒って」いる状態です。
「叱る」と「怒る」の違いを理解し、必要あらば適切に叱るようにしましょう。
子どもの前での夫婦関係を大切にする
子どもというのは本当によく親を観察しているものです。
親のちょっとした言葉遣いや行動を見て覚え、場合によってはマネしたりしますよね。
そんなよく観察している子どもですが、夫婦の関係性というのも見てないようでよく見ているものです。
子どもにとって夫婦の関係性を理解できないながらも観察することで、他者とのコミュニケーションを学んだり男女の違いを学んだりしていきます。
いわば、家庭というのは子どもにとって小さな社会の縮図であり、夫婦関係を通した学びの場でもあるんですね。
ですが、多くの親は子どものそのような観察眼を知りませんので、ケンカをしたり言い争ったり悪口を言ったりと、気にせず平気でそのような態度に出てしまいます。
それでは子どもにとっては悪いモチーフとなってしまい、成長とともにコミュニケーション事態に嫌悪感を覚えたり、感情を表に出せなくなるなど多くのデメリットを有する可能性があります。
ドラマのような良好で朗らかな夫婦関係を演じる必要はありませんが、せめて子どもにとってマイナスとなりそうな言動や態度は控えるべきと言えるでしょう。
日頃から夫婦としてお互いを理解する、相手の気持ちを尊重する、親しき中にも礼儀ありで過ごすなど、ちょっとした思いやりの気持ちが子どもの将来を左右していきますので。
おわりに
毒親になりたくない、子どもにとって適切な良い母親でありたい、という気持ちはとても素晴らしいものであり、子どもを思いやっている証拠です。
そして、その気持ちを持ちながら日々の言動や態度を見直し、実践していくことが毒親の連鎖を止める最大の力となるんですね。
毒親の連鎖を止めることはできますが、それにはまず絶対的に自分を信じること。そして、今回お話したことを頭に置き、少しずつでも良いので実践していくことです。
あまり難しく考えず、今回のお話がこれからの参考になれば幸いです。
~毒親問題・家族問題・親子問題の苦しみを軽くして、毎日を笑顔で過ごすために~
各種カウンセリングのご依頼は↓↓↓↓
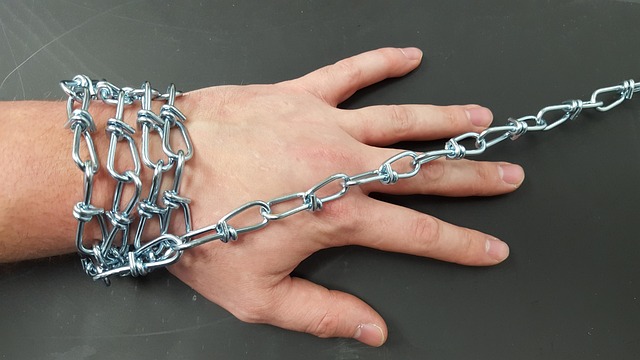


















コメントを残す