こんにちは。
家族問題解決専門カウンセラーの鈴木悦子です。
「自己肯定感」という言葉がありますよね。
この言葉はそのまま「自分」という存在を前向きに、肯定的に受け入れるというような意味です。
自己肯定感が高ければ高いほどちょっとのことでは折れない前向きな精神が宿りますし、あらゆる面で自信を持って行動できる、というメリットがあるものです。
ですが、毒親の元で育った多くの人は、この「自己肯定感」が低い傾向にあり、どちらかといえば気持ちが折れやすく、様々なことに対して自信を持てない、といった問題が生じます。
もしいま現在、小さなお子さんの子育てをしていれば、
「自分の子どもには、私と同じように自己肯定感の低い人生を送らせたくない」
「気がつけば、毒親と同じような否定的な言葉を使ってしまうんじゃないか」
というような不安や、毒親の連鎖に対する恐れを抱えているかもしれませんね。
しかし、安心してほしいのですが、自己肯定感というのは“毎日の言葉がけ”を工夫することで高まりやすく、定着していきます。
ですので、子どもの自己肯定感を育むための言葉がけを知り、それを意識して自分のなかで使っていくことが毒親からの連鎖を止め、良い子育てへとつながっていくんですね。
今回は、毒親育ちの子育ては完璧を捨てる理由、人はなぜ言葉がけに不安を感じるのか?不安を払拭するためにできる心の整えかた、そして子どもの自己肯定感を育むための言葉がけについてお話していきましょう。
目次
なぜ毒親育ちは「言葉がけ」に不安を感じてしまうのか?
「~しなさい!」
「お前はダメな子どもだ」
「ちゃんと我慢しなさい!」
あなたが小さな子どもの頃、親から「否定」や「我慢の強要」というのを日々浴びせられていませんでしたか?
親からのそういった言葉の数々は大人になったからといって勝手に風化することはなく、心の奥底にべったりと張り付いています。
時としてそんな小さな頃の体験がひょっこり顔を出し、嫌な気分を湧き上がらせてしまうこともあるでしょう。
また、
「私が受けたような嫌な言葉を子どもには使わない!」
と心に決め、日々子育てをいても、ついうっかり口調がキツくなってしまったり、八つ当たり気味になってしまうこともあるかもしれません。
母親というのはひとつの役割であり、母親という役割の前にひとりの人間ですので、場合によってイライラしたりカチンときたり、悲しくなったり怖くなったりと色んな感情が動きます。
人間というのは何かしら嫌なことがあり、イライラが募っていくと、それをどこかにぶつけたくなるもの。
ふとした瞬間に子どもに対して否定的な言葉を使ってしまい、
「ああ・・・私も毒親と同じことをしている・・・」
と拭っても拭っても取り払えない後悔の念を感じることもあるかもしれません。
そして、その後悔から強く完璧な母親像を描き、「子どもに嫌な思いをさせない、完璧な母親になる!」と改めての決意が生まれる可能性があります。
ですが、そもそも人間に完璧というものはなく、どこか抜けてしまったり、ちょっとミスをしてしまうことが本来の人間らしさとも言えます。
子どもの親として、ひとりの人間として、まずは完璧であることを捨てましょう。
完璧であるという姿勢を捨て、人間らしい未熟を認めていくことが、毒親育ちの子育ておいて「自己肯定感」を育む一歩となります。
子どもの自己肯定感を育てるための土台とは?親自身の「心の整えかた」
子どもの自己肯定感を育てる上で最も大切なこと。それは、
“親であるあなた自身の心に余裕があること”であり、あなた自身の“自分軸が整っている”状態を指します。
毒親の元で育った人は子どもの頃の経験からどうしても他人軸になりがちです。
これまで培ってきてしまった他人軸を切り離し、自分軸へとシフトしていくことで、親であるあなたの土台が整います。
ここからは、自分軸を培うための心の整えかたを2つお伝えしますね。
【1つ目】ネガティブ感情を「言語化」して手放していく
イライラや不安、モヤモヤといったネガティブ感情は心に溜め込んでしまいがちです。
感情というのはある意味生ものですので、溜め込み過ぎていくと腐ってきてしまい、気力や体力を奪うなど心身にダメージを与えます。
そうならないよう、日頃からネガティブ感情を手放していき、空気を入れ替えるように心を整える必要があるんですね。
手軽にできてなおかつ心を整えるのに役立つものは、
“ネガティブ感情を「言語化」して手放していく”
という方法でして、いわゆる「ジャーナリング」がそれにあたります。
この方法は過去に何度かご紹介していますが、改めてお話しますね。まずは紙やノートなど、そしてペンなど書くものを用意します。
それぞれ用意できたら、いま心のなかにあるネガティブ感情(不安、心配、イライラ、怒り、悲しみ、恐れ、など)を書き出していきます。
「私は○○○(たとえばイライラしている)」から書き出し、なぜイライラしているのか?どれほどイライラしているのか?どうしたいのか?バーッと紙に思うがまま書き出していきます。
書き出すだけ書き出し、心がちょっとでもスッキリしたら、その紙はビリビリに破き捨ててしまいます。
これを何度かくり返していくうちに心が軽くなり、次第に気分が整っていきますので。
とくに守るべきルールは存在しませんので、気の向くまま思うがまま、ババーっと書き出していきましょう。
【2つ目】インナーチャイルドに言葉をかけて優しく癒していく
心を整える方法の2つ目は、
“インナーチャイルドに言葉をかけて優しく癒していく”
というものです。
インナーチャイルドというのは、心のなかに住んでいるもうひとりの小さなあなたのこと。
インナーチャイルドが傷ついていたり元気を無くしていると、無気力になったり自己否定が強くなったり悪い影響が出てしまいます。
そうならないよう、インナーチャイルドに優しく話しかけ、望んでいる言葉をかけてあげることでインナーチャイルドは力を取り戻し、活力の源となるんですね。
こちらの方法も難しいことはなく、インナーチャイルドが望んでいるであろう温かな優しい言葉をかけてあげるだけです。
例えばですが、
「あなたはとても大切な存在だよ。いつもがんばってくれてありがとう」
「今日はとても疲れちゃったね。でも乗り越えたからスゴイよね」
「悲しいときもあるよね。我慢せずいっぱい泣いていいからね」
など、温かく優しい言葉、思いやりの言葉であればOK。
インナーチャイルドを癒すこと、すなわちそれは自分自身を癒すことにつながっています。
こう言われたら嬉しいな、こう言ってくれたら安心するな、という言葉を思い浮かべながら、インナーチャイルドにたくさんの温かな言葉をかけてあげましょう。
▶ 心理カウンセラー鈴木悦子へのカウンセリング依頼はこちらから
子どもの自己肯定感を育むための「肯定言葉」3つの真髄
心の土台が整ったら、いよいよ子どもの自己肯定感を育む具体的な「言葉がけの真髄」に移りましょう。
ここからは、子どもに対しておこなう“「肯定言葉」3つの真髄”についてお話していきます。
1、結果ではなくおこなったプロセスを褒める
多くの場合、できたか?できなかったか?という結果論に答えを求めがちです。
結果論は目に見えやすくわかりやすいためそこに集中してしまいがちですが、それでは毒親のパターンと何ら変わりありません。
そうではなく、どうやってその結果を出したのか?どう考えてどう動いて、その結果になったのか?
チャレンジの過程やがんばった努力に集中すること、結果にいたるまでのプロセス(過程)をしっかりと見極め、そのプロセスを褒めてあげましょう。
「〇〇しようとがんばってたね!すごいね!
「最後までできたね~!すごいすごい!」
など、プロセスを讃えるような言葉がけを考え、実際に伝えてあげましょう。
2、子どもの感情をそっくりそのまま受け止める
子どもは小さければ小さいほど、言葉によって自分の感情をうまく表現できませんよね。
子どもがいま感じている感情、たとえば怒りや悲しみを感じていたらそれを否定せず、そっくりそのまま受け止めてあげることが大切です。
専門用語では、いわゆる「共感」と「受容」というものになります。
これを上手に子どもとの会話に取り入れていくことで、子どもは受け止めてくれるという安心感から自己肯定感が育まれやすくなります。
たとえばですが、
「そんなことでいちいち泣かないの!」ではなく「とっても悲しいよね、悲しくてもいいんだよ」
「いちいち怒らない!」ではなく「とても腹が立ったんだね。それは怒りたくなるよね」
など、その感情を否定せずに肯定し、無理やり堰き止めないで受け止めていく。
子どもは純粋で素直ですので、親に感情を受け止めてもらえることで心が軽くなり、自己肯定感は増していきます。
感情を抑え込もうとするのではなく、共感と受容を使って迎え入れてあげましょう。
3、子どもの存在そのものを認める言葉がけ
子どもを褒めるというのは、何かを上手にできたから、良い子でいたから、ということではありません。
子どもの存在そのもの、子どもがそこにいるという事実を改めて受け入れ、無条件の愛情を言葉にしましょう。
こちらもたとえばですが、
「あなたがいてくれるだけでママは幸せだよ」
「生まれてきてくれてありがとう」
「○○ちゃんのことが世界で一番大好き」
など、愛情をしっかり言葉にして伝えてあげることが大切です。
子どもは存在そのものを愛されることで自信が身に着き、あわせて子どもの揺るぎない自己肯定感が形成されていきます。
ぜひ、たくさんたくさん言葉をかけてあげましょう。
おわりに
今回は、子どもの自己肯定感を育むために必要な言葉がけ、そこに伴う親としての心の整えかたなどお話しました。
毒親からの連鎖を断ち切り、子どもにとっての良い親としてできること、やるべきことがあります。
今回お話した内容を頭の片隅において、今日から明日からできること、できそうなことをぜひ実践してみてください。
豊かな心で豊かな子育てをしていくために。
今回のお話が少しでも役に立ったら嬉しいです。
~毒親問題・家族問題・親子問題の苦しみを軽くして、毎日を笑顔で過ごすために~
各種カウンセリングのご依頼は↓↓↓↓




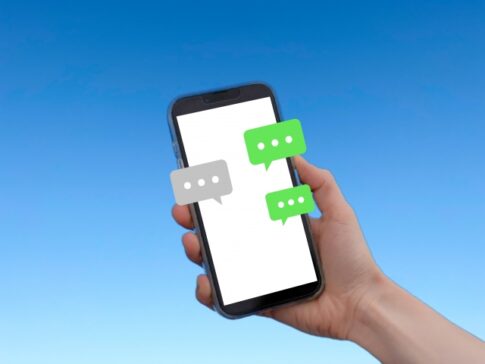














コメントを残す