こんにちは。
家族問題解決専門カウンセラーの鈴木悦子です。
「対人恐怖症」という、いわゆる神経症(心の病)があります。
対人恐怖症というのは人に対する怖さや不安の表れから人の視線や目線を避けるようになったり、人に近づけないといったことが起こる心理状態のことです。
昔から日本には対人恐怖症、視線恐怖症といった対人に対しての神経症がありましたが(海外には対人恐怖症は無い)、ここ数年で一気に増えたような気がします。
特に小さければ3~4才くらいから、20歳を超えた大人までどこか対人恐怖症的な感覚を覚えることがあり、社会生活に対して少なからず影響があるでしょう。
しかし、なぜここ数年で一気に対人恐怖症が増えたのか、その背景にはどのようなことがあるのでしょうか。
子どもの成長に大きな影響を与えた2つの社会的変化
近年、現代社会において大きく2つの大きな変化が訪れました。
まず一つ目、それは「スマートフォンやタブレットデバイスの普及」です。
今は右を見ても左を見てもスマホやタブレットを眺めている人は多く、ちょっとでも時間があればスマホ片手に見入っているような状態です。
特に電車の待ち時間や電車内においてスマホやタブレットを見入っている人は多く、電車内における60%ほどは見ているのではないでしょうか。
二つ目の変化は「マスク着用率の高さ」が挙げられます。
約4年ほど前に「新型コロナウイルス」が発生した影響によりマスクの着用率が爆発的に高まり、マスクを着用していない人は非国民扱いのような気配がしていました。
これは大手のマスメディアが大々的にマスクの着用を訴えたことで国民がそれを信じ、着用率が上がったという背景がありますよね。
現在はコロナウイルスの基準も変わり、風邪をひいていたり咳が出ている場合は別ですが、マスクの着用はしなくても良いことになりました。
しかしそれでもいまだ着用率がある程度高く、人間は習慣性の生き物だと改めて感じます。
実は、社会的に起こった2つの大きな変化、スマホやタブレット、マスクの普及がお子さんの影響に大変大きな影響を与えているのをご存じでしょうか。
スマホやマスクが子どもの成長にどのような影響を与えるのか?
子どもというのは生まれてから物心つく位までお母さんが四六時中寄り添い、子どもの世話をすることで子どもは心も身体も成長していきます。
児童心理学的にはおおよそ3才くらいまでには子どもの心の根幹が育ち、性格傾向が垣間見えるようになり、好き嫌いなどの好み、ある程度物事の判断がつくと言われています。
また、お母さんとの触れ合いや言語的、非言語的なコミュニケーションによって子どもの育ち方が変わってくるんですね。
ちゃんと子どもの目を見て話す、子どもの肌に触れる、子どもの近くにいてあげることで子どもは大きな自信がついたり人に対しての社会性を学んでいきます。
ですが、冒頭でお話した2つの社会的変化、スマホやマスクが子どもの成長に強い弊害を与えていることはあまり知られていません。
公園や道端、駅の構内や電車内、食事中にお母さんとお子さんが一緒にいるのを見かけますが、お母さんがちょっとした隙にスマホを取り出し見入っている光景が良く目に入ります。
もちろんスマホを見るのは自由なのですが、子どもが何か話しかけたり動作をしても目はスマホを向いており、子どもに顔を向けず手だけでベビーカーを動かしてあやしたり、人によっては「ちょっと待って!」と子どもに対して怒るお母さんもいます。
子育てにおいてとても大切なことは、いかに子どもの目を見て触れ合うか?コミュニケーションを図るか?です。
目はスマホを追いかけ子どもに視線を送らないのは子どもの心に大きな影響を与えてしまい、「自分はお母さんに必要とされていない」と感じたり、物心ついたとき人の目を見て話すことが出来なくなる可能性があるんですね。
大半の子どもは他者とのスキンシップ、コミュニケーションをお母さんから学びます。
お母さんが子どもの目を見て話さない、スマホに気を取られしっかり触れ合うことをしないと子どもは他人の目を見て話すことは出来ませんし、スキンシップやコミュニケーションが取れず他者との間に壁を作るようになってしまいます。
また、マスクを着用しているとお母さんの顔がわからなくなるので子どもは感情を読み取ることが出来ず、結果感情がわからない、感情を相手に伝えることが苦手となってしまいます。
多くの対人恐怖症は幼少期の親との関係性から生じると言われており、ここ数年若い世代に対人恐怖症や視線恐怖症が増えている要因がわかるような気がします。
せめて子どもと一緒にいるときはスマホを置いておく、マスクはしないなど、子どもへの影響を考慮してコミュニケーションやスキンシップを図ることがとても大切だな、と思っています。
終わりに
子どもが大人になったときの社会性や社交性、そのほとんどはお母さんから学びます。
子どもの目を見て話すことは心の触れ合いとなり、肌を触りスキンシップを取ることは身体の触れ合いになり、それにより子どもは他者との上手なコミュニケーションを図れるようになります。
スマホは特に依存性が高いものですので、お母さんが自らスマホと距離をとり、子どもとの触れ合いに時間を割くことがとても大切です。
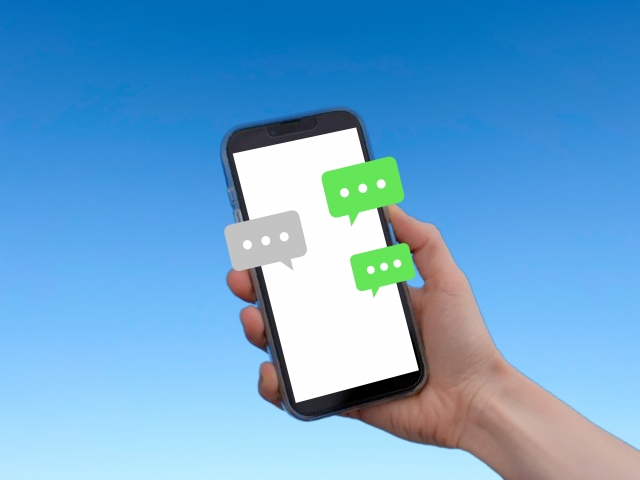


















コメントを残す